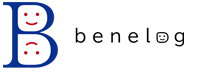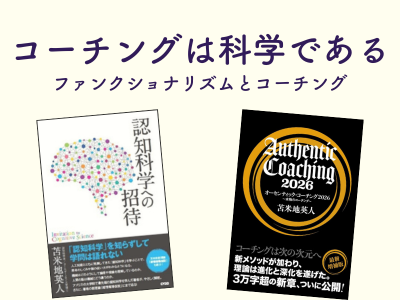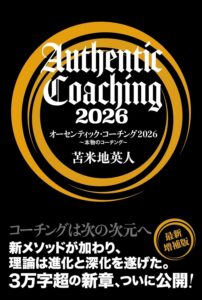コーチングは科学である。これは苫米地英人博士がコーチングについて語る際に常に強調することです。そして、コーチングが科学であると言う時、それは認知科学を意味します。しかしながら、最近は認知科学をベースにしていると謳うコーチングが世の中にあふれていて、そこでは「認知科学」が「最新の」という意味でコーチングを形容する言葉として使われているようです。
苫米地式コーチングも認知科学をベースにしています。「ベースにしている」というととても曖昧な表現なので、私は一人のコーチでしかないのですが、もう少し説明を加えたいと思います。
認知科学は、いま現在進行形で私たちの仕事や生活に大きな影響を与えつつある人工知能(AI)を研究する過程で発達して来た学問です。そして、『人工知能とは、人間の脳が行うことを機械でやろうという試み※』です。
要するにAIは、人の脳のような働きをする機械として研究、開発されて来たわけです。もっとくだけた言い方をすると、「AIは脳に似せた巨大なコンピューター」と言えるでしょう。
そのAI研究の初期には、まず、『人間の心理を機械にどう理解させるか、あるいは人間が使う自然言語を機械にどう理解させるか※』が大きな課題でした。
人間の心理と言っても、当時の心理学はまだ認知科学以前のもので、いわゆる行動主義とか構造主義とか言われるパラダイムで人の心が研究されていました。簡単に言うと、心の中がどうなっているのか、どのように働いているのかはブラックボックスのままで、外からの刺激(入力)に対する反応(出力)を見て(入力と出力の関係を見て)、心を理解しようとしていました。
例えば、苫米地博士がよく引き合いに出す「人間とは何か、どんな存在か」という例で説明すると、次のようになります。
『「人間を一回殴ったら驚いた。二回殴ったら怒った。三回殴ると死んだ」という観察結果から、「人間とは一回殴ると驚き。二回殴ったら怒り。三回殴ると死ぬという存在である」と定義※』できるというような考え方です。
少し極端な例ですが、これとあまり違わない考え方のもとで実際に研究が進められていました。でも、さすがにおかしいだろうということで出て来た新しいパラダイムが認知科学(Cognitive Science)であり、機能主義(Functionalism)です。
認知科学は『1970年代後期から1980年代初頭ぐらいの頃※』に登場しましたが、『刺激による反応ばかりを見るのではなく、心とか脳の「機能」に着目※』します。機能=function(ファンクション)だから、機能主義(ファンクショナリズム)です。
そして、ファンクションなのであれば、心の働きを「関数」(必ずしも、数式で表せるという意味ではありません)で表せるのではないかということで、コンピューターでAIを実現しようという動きが一気に進みました。
あらためて整理すると、認知科学とは『心とか脳の働きを関数で書き表すことができると考えて、研究する学問ということです。※』
★★★★
さて、長々と書きましたが、苫米地式コーチングではマインド(脳と心)の働き、すなわちファンクションへの理解が前提となっています。クライアントのマインドがどのように働いているのか、それをファンクションとして機能主義的に理解しようとします。
だから、コーチがクライアントに対して、こんな働きかけや質問をした時にこういう効果があったなどという「刺激と反応」についての情報を集めた質問集やテクニック集は苫米地式にはありません。
では、人類がどれくらいそのファンクションを理解しているのかというと、私はその答えを持ち合わせていません。ただし、苫米地英人博士は世界的な認知科学者であって、苫米地式コーチングはクライアントが現状の外側に心からやりたいと思うものを自ら見つけて、それを達成しようとするのをサポートするメソッドとして苫米地博士が開発したものです。だから、苫米地式のコーチは、少なくともコーチングの枠組みの中で関係するファンクションについては熟知していると断言することができます。
最後に、11月に『オーセンティック・コーチング2026 ~本物のコーチング~ 』(苫米地英人著)が発売され、認知科学的にアップデートされた苫米地式のコーチング理論が紹介されています。この本でなお一層、コーチングが科学であると感じることができますので、コーチングに興味がある方は、ぜひ一度お読みになることをおすすめします。
※の箇所は「認知科学への招待」 Kindle版(苫米地英人著)より引用